朝日新聞【 声 】に、『お霊膳・盆飾り こころ安らぐ』
- sajipura
- 2018年8月12日
- 読了時間: 3分
更新日:2018年9月14日

協会の記事ではありません。
安養寺住職 のfbより紹介です。
8月19日、朝日新聞【 声 】に、『お霊膳・盆飾り こころ安らぐ』というタイトルで、拙僧の投稿が掲載されました。
★この文を書いた時に、お盆の時期にこの文はもっと多くの人に知らせたいと思いました。また、広く一般にも受け入れられるんじゃないかと直感し、初めて投稿してみたという次第です。 二三日して大阪朝日新聞から電話がきて、編集者の方と話しました。いろいろ尋ねられた後、逆になぜ私の投稿を採用したのかと尋ねました。
編集のWさんが言うには、「お盆のこの時期全国のたくさんの人がそれぞれの思いで亡くした人を偲び一連の仏教行事が行われます。そのなかで、お坊さんがその一人ひとりのこころを理解しようとして、庶民の目線で仏壇や尋ね先の方を見ている姿に、広く共感されると感じて採用することにしました。」と、言葉を頂きました。 まことに有り難いことです。 生あるものに幸あらんことを 吉水秀樹 三拝
※原文は下記です。
『お霊膳を知っていますか?』 8月1日からの14日間で約300軒の檀家へ棚経に参上します。私の側から見ると棚経は、「喜び」を与える実践になります。抜苦与楽といいますが、「苦しみを除いて、楽を与える」ことが理想です。さて、実際に喜びを与えられているのでしょうか? まず、私に喜びがないと喜びを与えることはできません。 連日30℃を越える猛暑のなか、300軒のお家を訪問することは苦行に近いです。頑張ってできる勤めではありません。まず、朝に冥想をして、力を抜いて淡々こなしています。その棚経での私の楽しみは「お霊膳」見ることです。お華やお菓子の盆飾りが、整然と荘厳された仏壇は見ているだけでこころの安らぎになります。なかでも亡くなった人への優しさや思いやりのこもった「お霊膳」を見ると、こころが震えることがあります。 毎年、木幡地区のKさん宅へお参りすると、その整然とした仏壇の荘厳とこころのこもったお霊膳に感動します。奥様は数年前にご主人を亡くされて、毎年私が訪問する時間に合わせて、お米を炊いてお霊膳を用意されます。炊き立ての湯気があがっていて、ツヤツヤしたご飯と色とりどり、おかずを見ているだけで私のこころが安らぎます。そして、そのお霊膳を作られた奥様へ見たとおりの私の喜びをお伝えします。奥様は涙を浮かべて喜ばれました。
※ 実に初期仏教に出会って、毎朝気づきの冥想でこころの静寂を得て、棚経に出かけるので、これもお釈迦さまはじめ、たくさんの先人祖師・長老さまの功徳の賜物です。このこころを、「ナモー タッサ バガワトー アラハトー サンマー サンブッタッサ」と言うのでしょう。毎朝唱えるパーリ語の偈文です。
※二枚目~四枚目の写真が実際のKさん宅の「お霊膳」と「仏壇の荘厳」です。その他は私が今年訪問した檀家のお霊膳と、最後は当山安養寺施餓鬼会のお霊膳です。
◆画像上の矢印をクリックすると、次の画像が表示されます。




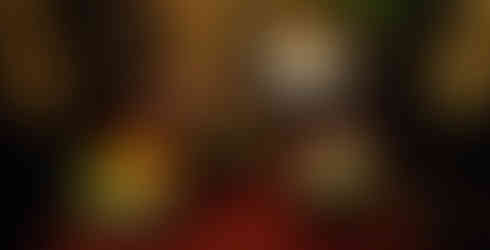


























コメント